こんにちは。
配当サラリーマンの“いけやん”です。
この記事では、
分散効果を得るには、何銘柄ほどに分けて持てば十分か?
について書きます。
目次
卵を1つのカゴに盛るな(銘柄の分散保有)
分散投資の大切さを説く、よく聞く格言です。
1つの銘柄に集中するよりも、複数の銘柄に分散させて保有したほうが、”何となく安全”
なのは直感的には正しい気がします。
たくさんの銘柄を持つことで、どれか1つの銘柄が下がっても、他の銘柄の上昇によって損失がカバーされるため、ポートフォリオ全体の安全性が高まります。
では、いったい、何銘柄ほどに分けて持てば、分散効果を享受できるのでしょうか。

【結論】分散効果は「20〜30銘柄」で十分得られる
結論から申し上げると、分散効果をしっかり得るには20〜30銘柄に分散すればよいと思われます。
これ以上は、分散効果は逓減する一方、管理コストが大きくなります。
多くの銘柄に分散すればするほど、分散効果は大きくなりますが、20〜30銘柄を超えるとその効果がサチレーション(効果が横ばいになって増えなくなる)することが分かっています。

N銘柄に分散したら、リスクは√N分の1になる
統計学の数式を使って、確認していきましょう。

保有銘柄をN種類に分散した場合、1銘柄集中投資に対して、運用成績のばらつきリスクは1/√N倍になります。
2銘柄だと、0.71倍3銘柄だと、0.58倍10銘柄だと、0.32倍30銘柄だと、0.18倍50銘柄だと、0.14倍100銘柄だと、0.10倍
となります。
※厳密には、保有銘柄が互いに独立(相関係数がゼロ)である場合に限ります。

下のグラフは、保有銘柄が増えるにしたがって、リスクが減少する様子を表しています。
横軸:保有銘柄数 に対し、縦軸:リスク比(1銘柄保有時を1とした場合)です。

初めは分散効果が大きい
このグラフを見ると、
分散効果によるリスク低減は、保有銘柄が少ない時は、保有銘柄を増やすことによるリスク低減効果(分散効果)が大きく、一気に減少していることがわかります。
特に10銘柄ぐらいまでの勢いがすごいですね。
分散しすぎると、分散効果の伸びが悪くなる
これに対し、保有銘柄が多くなると、そのリスク低減効果(分散効果)の勢いはだんだん下がり、20〜30銘柄あたり以降は、グラフが横ばいになっていることがわかります。
つまり、これ以上、包有銘柄を増やしても分散効果は(多少は増えるものの)増え方が鈍る、ということです。
下の表でも、途中から保有銘柄数を増やしてもリスクが下がるペースがどんどん逓減していることがわかります。
「株式投資のリスク」と「統計学の標準偏差」
「株式投資における価格変動(ばらつき・リスク)」は、「統計学の標準偏差」に対応しています。

株式投資のリスク(ばらつき)とは
ある銘柄の平均的な年率リターンが+5%だとしても、毎年5%ジャストで収益が出るわけではなく、+11%だったり、-3%だったり、「変動」します。

横軸:〇年目 縦軸:毎年のリターン
上のグラフでは、毎年のリターンは変動していますが、20年間で平均すると、+5%となることがわかります。
この「平均5%に対する平均的な差」が標準偏差です。
株価変動の小さな銘柄は、リスクが小さい(株価は安定しているが、大きくも上がらない)株価変動の大きな銘柄はリスクが大きい(大きく上がることもあるが、大きく下がることもある)

毎年の分布が正規分布であると仮定すれば、
毎年、60%の確率で、(100年に60年は)標準偏差(1σ)の範囲に収まります。

また、毎年、95%の確率で、(100年に95年は)標準偏差の2倍(2σ)の範囲に収まります。

統計学における標準偏差
統計学における標準偏差も、株式投資のリスク(ばらつき)と同じような意味で使われています。
標準偏差とは
標準偏差とは、
ある母集団から何個かのサンプルを抜き出した時、平均値に対し、平均的にどれだけ差があるか
です。

標準偏差同士を足し合わせる計算方法(標準偏差の加法)
標準偏差同士を足し合わせる場面は、ものづくりの世界でもあります。
「ある固定座面に1枚の板部品をネジで締めつける場面」があったとします。
この時、ねじが固定座面からあまりに飛び出るのは、何かに当たってしまい、よろしくないので、最悪でも何センチほど飛び出るか、想定する必要があります。
標準偏差の考え方を使って、
座面~ねじの頭(X)がどの程度飛び出しうるか(=飛び出す側にばらつくか)
を計算することができます。

工業製品の「寸法」と「公差」
寸法
ねじなどの工業製品には「この大きさで作りなさい」という寸法指定があります。
例えば「10cm」など。
公差
といっても0.1ミリもズラさず、ちょうど10cmジャストにすることは不可能です。
どうしても要求の寸法とは僅かな差が出てしまうので、
「これだけはズレてもいいよ」
「この範囲には納めてくださいね」
という寸法公差が設定されます。
例えば、「±0.1cm」など。
かくして、部品やネジには、
目標の「寸法」 と ズレていい範囲である「公差」
が決められます。
(10±0.1cmなどと書きます)
ここでは、
ねじ寸法と公差(a)が 2±0.5cm
板部材の寸法と公差(b)が1±0.4cm
だったとしましょう。

この時、 Xの平均値Xave と Xの公差Xσ はいくらになるでしょうか。
平均値の足し算は「単純足し算」で分かる
平均値に関しては、
各構成要素 ねじ寸法(a)と 板部材(b) の合計(単純足し算)で
Xave = 2 + 1 =3cm と計算できます。
公差の足し算は「単純足し算」にはならない
一方で、公差についてはどうでしょうか。
単純足し算とし、最も飛び出してしまう場面として、
0.5+0.4=0.9cm
を考慮するのは、工業製品の設計上、あるべきかもしれません。
しかし、実際にこんなことはあるのでしょうか??
最悪同士が出会うことは、そうそう起こりえない
ねじ寸法(a)と 板部材(b)の両方が公差ギリギリに作られてしまい、これらが組み合わさってしまうことはかなり稀です。
部品とネジの全てが最大ギリギリに作られることなんてまずないし、どれがが大きい側(+側)に作られたとき、他のどれがは小さい側(-側)作られることもあるので、
実際にはキャンセルされ、平均に近づくはず
です。
まさにこの辺りは、株式の分散効果と同じ考えです。
(みんなが揃って下がることは、大暴落時以外、なかなかない。通常は、下がる銘柄もあれば、上りる銘柄もあり、お互いがカバーしあう。)
公差の足し算は「二乗和平方根」で分かる
では、結局のところ足し合わせた公差(Xσ)はいくらぐらいと見積もるべきかというと、

という式で計算されます。
それぞれに二乗して、足して、ルート(平方根)をとって計算するので、二乗和平方根といわれます。
さすがに、単独の公差0.5cm や0.4cmよりは大きいものの、
単純足し算の0.9cmよりは小さい
という結果となり、直観に近い数値となることが確認できます。

【まとめ】2つ以上組み合わせれば、ばらつきが抑えられる。株の分散効果は20~30柄で十分。
工業製品の公差の足し合わせで見たように、2つ以上のものを組み合わせることで、ばらつき(=標準偏差・リスク)を低減することができることを確認しました。
株に関しても同じで、複数の銘柄を組み合わせることで、ばらつきを抑えることができます。
一方、ばらつき低減の効果は、銘柄数が少ないときは十分得られるものの、銘柄数が増えるに従い、その効果が薄れることも確認しました。
保有銘柄が増えるとその管理が面倒になるため、分散効果を狙うことだけを考えた場合、20~30銘柄に分散すれば、その効果が十分といえるでしょう。
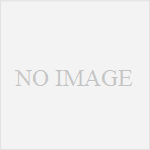
コメント